開発手法とは?6つの種類と違い、選定ポイントを解説
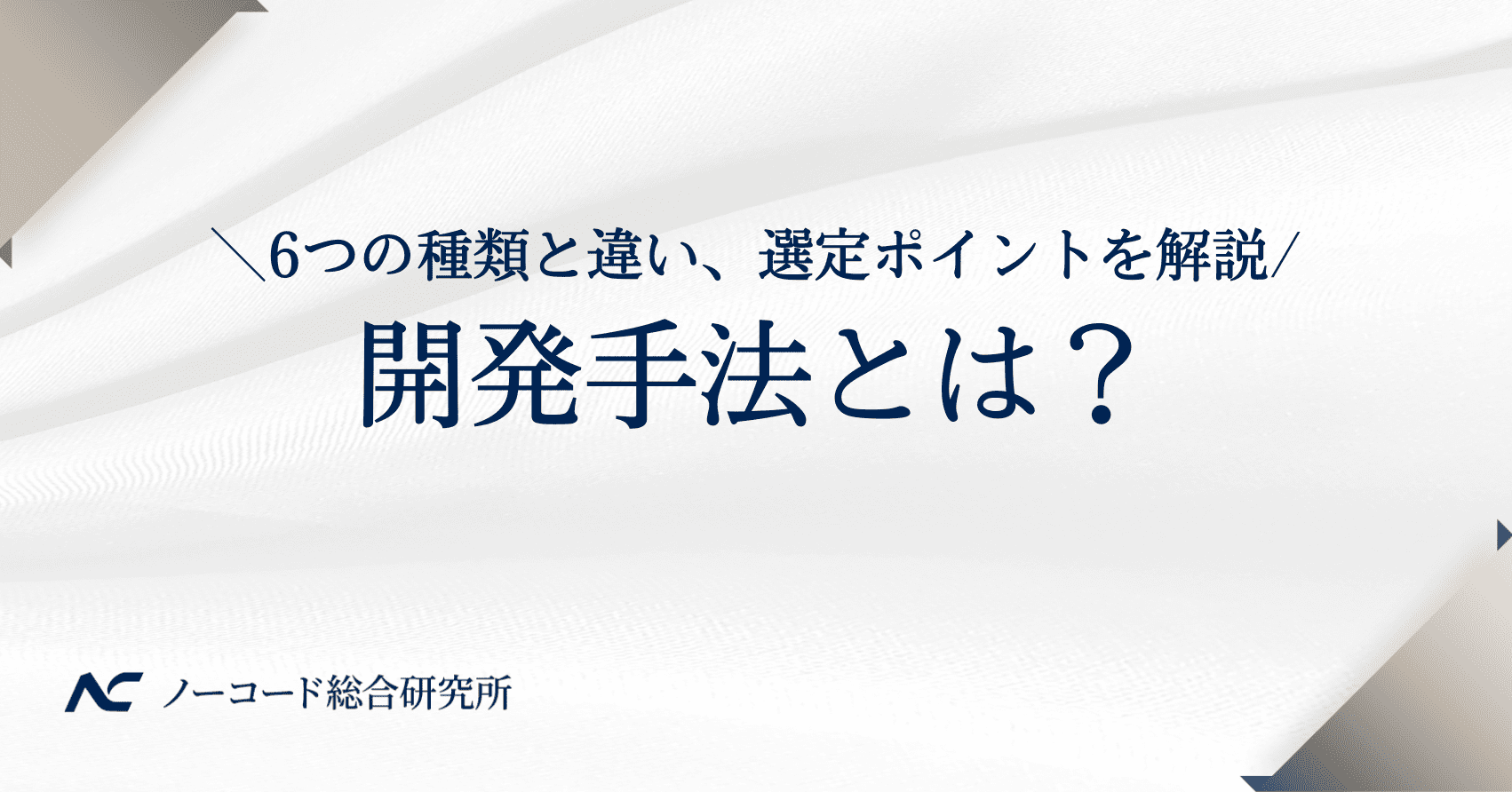
システム開発の現場では、目的や体制に応じた「開発手法」の選定が欠かせません。
ウォーターフォール開発やアジャイル開発といった代表的な手法に加え、近年ではノーコード/ローコード開発といった非エンジニア向けの手法も注目されています。
効率的にプロジェクトを進行させるには、それぞれの特徴やメリット・デメリットを正しく理解し、自社に合ったスタイルを見極めることが重要です。
本記事では開発手法の基本から6つの代表例、選定のポイント、ノーコード開発などの最新トレンドまでを紹介します。
開発手法とは?

システムやアプリケーションの構築には、あらかじめ定めた進行ルールが欠かせません。適切な手法を選ぶことで、品質の確保や作業効率の向上が期待できます。
プロジェクトの成功を左右する「開発手法」について、基本的な考え方から具体的な活用効果まで順を追ってご紹介します。
開発手法の定義と役割
開発手法とは、システムやアプリケーションを構築する際に採用される作業の進め方や設計ルールのことを指します。
企画から運用に至るまでの一連の工程をどのように設計・管理するかが明確になることで、関係者の意思疎通がスムーズになり、工程ごとの作業漏れや無駄なやり直しを抑えやすくなるのです。
開発にかかわる人員の技術レベルやチーム構成、納期やコストなどの条件に応じて最適な手法を選ぶことで、品質と効率を両立させることが可能となります。
なぜ開発手法が重要なのか?
システム開発では、要件のずれやスケジュールの遅延といったトラブルが起こりやすいものです。
こうした問題を未然に防ぐために、プロジェクトの枠組みを明確に整える「開発手法」の選定が求められます。
計画通りに進めるための土台を整えることで、途中での方針転換やリスク発生時の対応も取りやすくなり、最終的な成果物の品質向上にもつながります。
技術だけに依存せず、チーム全体の統率を保つための仕組みとしても、手法の選択は重要な判断材料です。
開発手法を使うことで得られる効果
適切な開発手法を導入することで、プロジェクト管理がしやすくなり、開発の見通しが立ちやすくなります。
たとえばアジャイル型なら柔軟性が増し、ウォーターフォール型であれば計画性が強まるなど、目的に応じて得られる効果が異なります。
また、プロジェクト関係者間の認識を揃えやすくなり、情報共有が円滑になるため、誤解による工数ロスの抑制も可能です。
開発の途中経過が可視化されることで、経営層や外部との調整も行いやすくなるという点も、大きな利点です。
開発手法導入時の注意点
開発手法を導入する際は、プロジェクトの性質や目標との整合性を丁寧に確認する必要があります。
たとえば短納期の案件に対して工程が複雑な手法を選ぶと、かえって進行を妨げる結果になりかねません。
また、手法に沿うことに固執しすぎると、現場の柔軟な判断が失われるおそれもあります。
現実の業務とのバランスを見極め、目的達成に有効かどうかを見直しながら運用することが、失敗を防ぐ上で欠かせません。
ノーコードでのアプリ開発なら「ノーコード総合研究所」
ノーコード総合研究所は、ノーコードツールを活用し、従来の約3分の1の期間と費用でWebアプリや業務システムを開発している、国内最大規模の受託開発会社です。開発だけでなく、新規事業の立ち上げ支援や業務効率化、AI導入まで幅広く対応しています。
企画段階からUI/UX設計、マーケティング支援まで一貫して伴走する体制を整えており、技術だけでなく事業成長にも貢献することを重視しています。ノーコードに関する豊富な知見と実績を活かして、柔軟に支援可能です。
開発手法の種類6選

プロジェクトの目的や状況に応じて、採用すべき開発手法は変わります。ここでは代表的な6つの手法について、それぞれの特徴や活用シーンを分かりやすくご紹介します。
| 開発手法 | メリット | デメリット | 活用例 |
|---|---|---|---|
| ウォーターフォール開発 | 工程が明確で進行管理がしやすい。スケジュールが立てやすく品質管理に適している | 途中での仕様変更に弱く、計画ミスが後工程に響きやすい | 要件が明確な基幹システムや公共事業など、変更が少ない大規模プロジェクト |
| アジャイル開発 | 柔軟な変更対応が可能。顧客フィードバックを取り入れやすい | 進行が見えづらく、管理が難しい。スキルの高いチームが必要 | スタートアップの新規サービスや頻繁な仕様変更が想定されるWebアプリ開発 |
| スクラム開発 | 短期間で成果を出しやすく、自己組織化による生産性向上が期待できる | 高頻度のミーティングと密な連携が求められ、体制整備が不可欠 | 少人数での短期開発や、チーム主導で進行する社内ツールの改善プロジェクト |
| プロトタイピング開発 | 完成前に実物に近い試作品を確認でき、ユーザー視点での改善が進めやすい | 試作コストがかかりやすく、納期や予算に余裕が必要 | 完成形が定まっていない新規アプリや、ユーザーの使用感を重視するサービス開発 |
| スパイラルモデル | リスクを評価しながら進行でき、品質重視の大規模開発に向いている | プロセスが複雑で時間も費用もかかる。進行管理に高度な対応が必要 | 金融や医療など高信頼性が求められ、段階的に要件を確定させていく大規模案件 |
| DevOps | 開発と運用を一体化でき、リリースの高速化や継続的な改善が可能 | 導入には組織全体の理解とツール整備が必要で、初期対応に手間がかかる | クラウド環境を利用した継続的リリースが求められるWebサービスやSaaS製品 |
1.ウォーターフォール開発
ウォーターフォール開発は、設計から運用までの工程を段階的に進める手法です。各ステップを完了してから次に進む構造であるため、計画通りに物事を進めたい場面で特に力を発揮します。
事前に仕様やスケジュールをしっかり固めておくことで、品質管理や進行の見通しがしやすくなるのが特徴です。
たとえば、行政機関が関与する公共事業や、仕様が明確な業務システムの構築に向いています。一方で、柔軟な仕様変更には対応しづらく、途中での方針転換が困難な点には注意が必要です。
2.アジャイル開発
アジャイル開発は、短い期間で機能を小分けにして開発しながら、改善を重ねていく手法です。状況の変化に合わせて調整しやすく、顧客の要望にリアルタイムで応えられる柔軟性が評価されています。
特にスタートアップ企業のようにスピードを重視する環境や、初期段階で仕様が固まりきっていないプロジェクトに適しています。
Webサービスやスマートフォン向けアプリの開発に多く用いられる手法ですが、チーム内での連携力や自律的な判断力が求められるため、運用には一定の経験値が必要です。
アジャイル開発についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
アジャイル開発によるアプリ開発の効率化と成功の秘訣
3.スクラム開発
スクラム開発はアジャイルの一種でありながら、明確な役割分担と短期的な開発単位「スプリント」によって効率的に成果を出していく手法です。
チーム全体で課題解決に取り組む文化が重視されており、自己組織的なチームによる改善と迅速な開発が特徴です。
たとえば、社内ツールのアップデートや少人数で行う短期プロジェクトに向いています。
進捗確認のためのミーティングを頻繁に行うため、メンバー間の密なコミュニケーションと体制整備が重要です。
4.プロトタイピング開発
プロトタイピング開発は、完成前の段階で試作品を作成し、利用者の意見を取り入れながら開発を進める手法です。
ユーザーの要望や使用感を反映しやすいため、完成イメージがまだ明確でない状態でも方向性を固めていきやすい利点があります。
新しいアイデアを形にしていくスタートアップのプロジェクトや、ユーザー体験を重視するサービス開発に適しています。
ただし、プロトタイプを何度も作るため、コストやスケジュール面では余裕を持った計画が必要です。
5.スパイラルモデル
スパイラルモデルは、開発を段階的に繰り返すことでリスクを抑えながら進める手法です。各サイクルで設計や評価を重ねるため、仕様の不確実性が高い段階でも柔軟に対応できます。
医療や金融など信頼性が重視される領域で活用される一方、工程が多く時間やコストが膨らみやすい点が課題です。綿密な管理体制が必要となるため、体制づくりも重要になります。
段階ごとの慎重な構築が必要なプロジェクトにこそ力を発揮するモデルといえます。
6.DevOps
DevOpsは、開発(Development)と運用(Operations)の連携を強化することを目的とした手法です。
アプリケーションの設計からリリース、その後の保守・改善までを一体化し、自動化ツールなどを活用して効率化を図ります。
継続的インテグレーション(CI)や継続的デリバリー(CD)といった考え方とも親和性が高く、頻繁なリリースと素早いフィードバックサイクルを実現できます。
クラウド環境を前提としたプロジェクトで特に有効です。
【プロジェクト別】開発手法を選ぶ際のポイント

開発手法を選ぶ際には、プロジェクトの特性や社内体制を踏まえた判断が求められます。ここでは、実際の選定に役立つ3つの視点から考え方を整理していきます。
開発手法選定で最初に考えるべきこと
最初に検討すべきなのは「開発の目的」と「優先順位」です。納期厳守が最重要なのか、ユーザー体験を重視するのか、それともコストを抑えたいのかなどの目的が明確になることで、適した開発手法が見えやすくなります。
たとえば、柔軟性を重んじるならアジャイル開発が有力ですし、計画通りの進行が求められるならウォーターフォール開発が適しています。また、開発チームの経験値やスキルも無視できない要素です。
チーム体制や既存の業務フローとマッチする手法を選ぶことが、結果的に近道となります。
プロジェクト規模と手法の相性から考える
開発規模の大小は、手法選定に大きく影響します。
小規模な開発ではアジャイル開発やプロトタイピング開発が適しており、少人数でも迅速に検証・改善が進められるため、開発コストや時間の削減にもつながります。
一方、大規模プロジェクトでは、工程が明確に整理されたウォーターフォール開発やスパイラルモデルのような手法が有効です。
特に品質管理が重視される業務システムや官公庁向けの案件では、段階的かつ厳密な進行が求められるため、構造的な手法が安定した成果をもたらします。規模と目的のバランスを見極めることが重要です。
導入事例を参考にする
自社にとって最適な開発手法を見極める際は、他社の導入事例を調査するのも有効な手段です。
たとえば、似た業界・業種の企業がどのような開発体制で成果を上げたのかを知ることで、手法選定の方向性がより具体化されます。
特に、クラウド環境を活用したDevOpsの導入事例や、短期間でサービス改善を重ねたアジャイル開発の成功例は、多くのヒントを与えてくれます。
導入後にどのような課題があったかもあわせて確認しておくと、自社で応用する際の注意点や改善策を事前に把握でき、手戻りのリスクを減らすことが可能です。
ノーコード/ローコード開発の基本を押さえることも大切

非エンジニアでもシステム構築に関われる手段として注目されているのがノーコード/ローコード開発です。その特徴や評価方法、導入の効果やリスクについて順を追って整理していきましょう。
ノーコード/ローコード開発の考え方
ノーコード/ローコード開発とは、プログラミングの知識がなくてもアプリケーションや業務ツールを作成できる手法です。
ノーコード開発はビジュアル操作のみで完結し、ローコード開発は一部のコード記述で柔軟性を持たせる開発方式となります。
専門知識を持たない業務担当者でも操作しやすく、開発のハードルが下がる点が特徴です。
システム開発を専門職だけでなく現場担当者も巻き込んで進められるようになったことで、部門主導の改善活動が加速しやすくなっています。
ノーコード/ローコード開発の評価軸
この手法を選ぶ際は、「内製化の実現性」「ツールの自由度」「拡張性」といった観点で評価する必要があります。
単に操作が簡単という理由だけでは、運用フェーズでの対応が難しくなる恐れがあるため注意が必要です。
また、ツールによっては独自仕様やロックイン構造が存在するため、長期運用や将来的な機能追加を見据えて選ぶことが求められます。
操作性と開発効率だけでなく、組織内でどのような体制で活用できるかも含めた多角的な判断が重要です。
ノーコード/ローコード開発による効果
開発期間の短縮やコスト削減だけでなく、社内のITリテラシー向上や業務改善のスピードアップといった効果も期待できます。
とくに現場主導でシステムが構築されることで、実務に即した仕様が反映されやすくなり、使い勝手の良いツールが生まれやすくなります。
また、改修や追加機能の開発が容易になるため、試行錯誤を重ねながら柔軟に運用を改善していく姿勢とも相性が良いです。ビジネス環境の変化に迅速に対応するための手段として注目されています。
ノーコード/ローコード開発の注意点
便利に見えるノーコード/ローコード開発ですが、導入前に押さえておきたい注意点もあります。
たとえば、ツールによっては細かな制御が難しく、要件に応じた柔軟な設計が実現しづらいケースがあるのも事実です。
また、運用管理の責任範囲が曖昧になると、トラブル時に対応が遅れる可能性もあります。
さらに、技術的な限界に直面したときに、社内で対応できる人材がいないと外注コストがかさんでしまう恐れもあるため、導入時には活用範囲と限界を見極めることが重要です。
ノーコード開発についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】ノーコードで始めるソフトウェア開発!未経験者でもアプリを作れる時代の最前線
まとめ
開発手法の選定は、単なる技術選びではなく、プロジェクトの成功率を左右する重要な判断です。
ウォーターフォール開発やアジャイル開発といった王道手法に加え、スクラム開発やDevOps、さらに近年ではプログラミングの知識がなくても作成できるノーコード/ローコード開発など、多様な選択肢があります。
それぞれの特徴を踏まえたうえで、自社の目的や体制に最もフィットする手法を見極めることが、円滑なシステム開発につながります。
導入事例や評価軸も参考にしながら、現場で本当に活用できる開発スタイルを確立していきましょう。


