ローコード開発ツールの価格とは?無料プランや人気のツールを比較
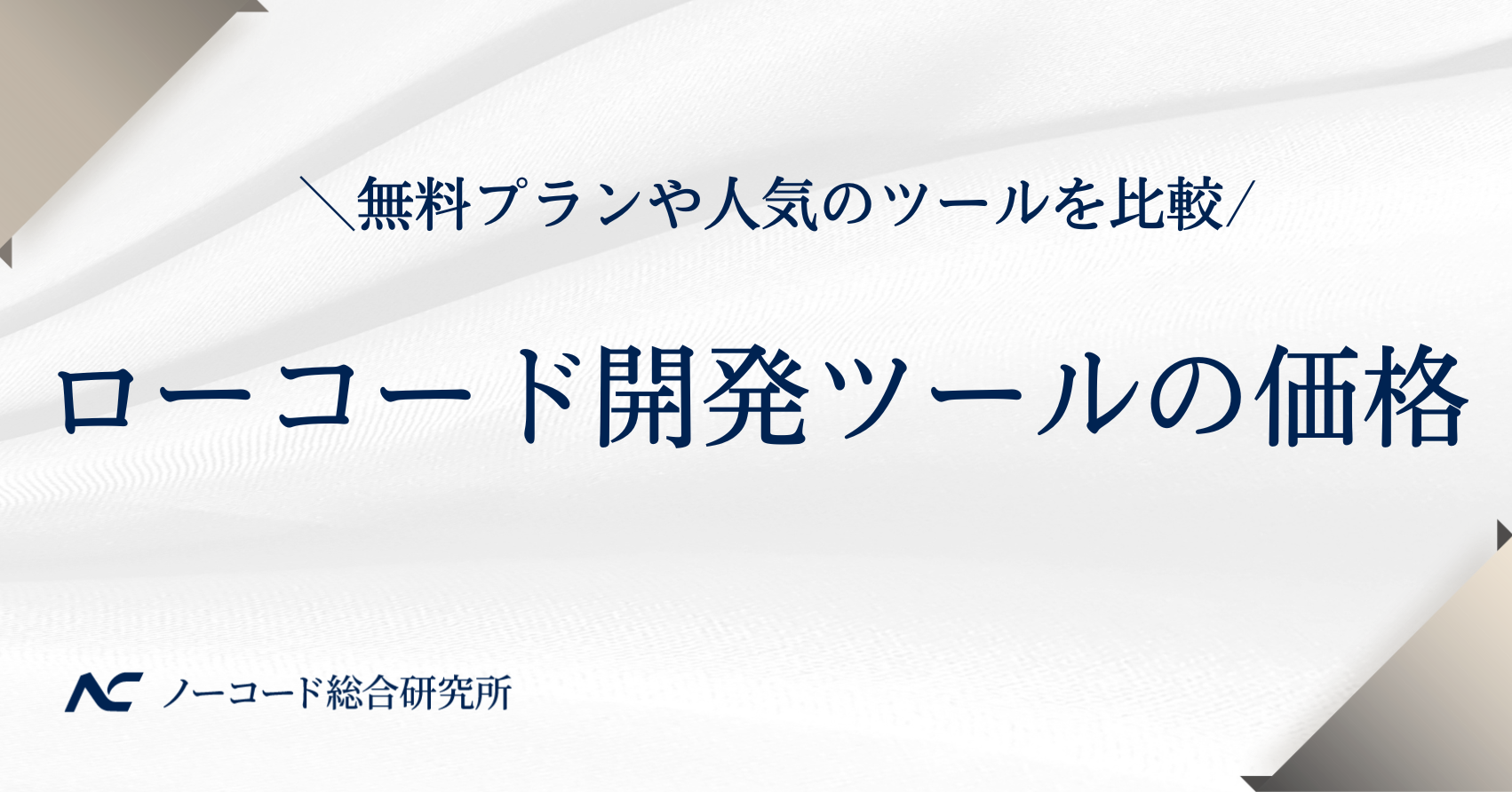
近年、DX推進や業務効率化が求められるなかで、注目を集めているのが「ローコード開発ツール」です。専門的なプログラミングスキルがなくても業務アプリをスピーディに開発できることから、非エンジニアの部門でも導入が進んでいます。
一方で、価格や機能、導入形態に関する情報は分かりづらく、比較検討に悩む担当者も少なくありません。この記事では、ローコード開発ツールの基本知識から料金相場や無料ツールの特徴などを詳しく解説します。自社に最適なツール選びの参考にしてください。
ローコード開発ツールの料金体系|相場と費用感
ツール選定において料金体系は重要なポイントです。ここでは料金体系の違いや、価格の目安について解説します。
ユーザー単位課金の価格レンジ
ユーザー数ごとに料金が発生する課金体系も一般的です。1ユーザーあたり500〜5,000円程度が目安で、利用人数が多いほど割引プランが適用されるケースもあります。
とくに多くの部署での利用を検討している場合は、ユーザー増加によるコスト変動に注意が必要です。
主な料金体系は「月額固定制」と「従量課金制」
ローコードツールには、あらかじめ定められた月額料金を支払う固定制と、利用人数や機能に応じて料金が変動する従量課金制があります。導入目的に応じて選択が必要です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、将来の運用負荷も見据えた検討が大切です。
初期費用の必要性
ツールによっては初期費用が必要な場合があります。とくに導入支援やカスタマイズ、サーバー構築などが発生するケースでは、3〜10万円程度の費用がかかることもあります。
予算計画には初期投資とランニングコストの両方を組み入れることが重要です。
有料ツールの導入コスト例
多くの有料ツールでは、月額利用料が数千円から十数万円までと幅があります。安価なツールは機能が限定されていることが多く、価格に見合った機能性が問われます。
目的や規模に応じて必要十分な機能を選定することが、コスト最適化につながります。
月額料金の相場感
ツールの提供形態や機能範囲によって異なりますが、月額3,000〜12万円程度が一般的な価格帯です。企業規模や目的に応じて適切なプランを選ぶ必要があります。
また、価格だけでなく導入後の保守サポート内容も確認しておくと安心です。
無料トライアルと有料プランの違い
ほとんどのツールには無料トライアルがありますが、保存容量や外部連携機能、ユーザー数に制限があることが多いです。本格導入の前には必ず確認しておきましょう。
トライアル時には、実際の業務で問題なく使えるかどうか、テスト的に利用してみることが大切です。
高額なツールと低価格ツールの差
高価格帯のツールは機能が充実し、サポート体制も整っています。一方で低価格のツールはシンプルな操作性が魅力ですが、対応範囲に制限がある場合もあります。
導入目的と費用対効果のバランスを見極めながら比較することが大切です。
無料で使えるローコード開発ツール
コストを抑えて導入したい企業にとって、無料ツールの存在は非常に魅力的です。ここでは代表的な無料ツールや選定の注意点を紹介します。
無料プランがある代表的なツール
AppSheet、Platio、kintone、Forguncyなどが無料プランを提供しています。それぞれの制限内容や機能を比較して導入を検討しましょう。
とくに中小企業では、コストを抑えつつ業務改善を図るための第一歩として無料ツールの活用が効果的です。
機能制限とライセンスの違いに注意
無料ツールでは、利用可能な機能や保存件数、ユーザー数などに制限がある場合が多いです。また、商用利用の可否がライセンスによって異なる点にも注意が必要です。
無料で始めて有料に移行するタイミング
導入初期は無料プランで使用感を確かめ、業務にフィットした段階で有料プランに移行するのが一般的です。段階的な導入が失敗リスクを軽減します。
完全無料とフリーミアムの違い
完全無料のツールは機能が限定される傾向にありますが、フリーミアム型は有料プランへの拡張が可能です。将来的な運用も視野に入れて選ぶことが重要です。
企業の成長や業務の拡大に応じてスムーズに移行できるかどうかも重要な評価ポイントです。
自社に向いている無料ツールの選び方
自社の業務に必要な機能が無料プランで満たせるかどうか、将来の拡張性はどうか、導入サポートがあるかなど、多角的な視点で選定することが求められます。
アプリ開発に必須の開発ツールについてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【完全ガイド】アプリ開発に必須の開発ツール|選び方とおすすめツールを徹底解説!
人気のローコードツールを比較
ツール選定に迷った際には、実績や機能、価格帯を比較することが有効です。ここでは主要ツールの特徴を整理します。
機能性と価格のバランスが良いツール
ForguncyやAppSuiteなどは、中小企業にも導入しやすい価格帯です。しかし、業務効率化に必要な基本機能が揃っているため、人気があります。
中小企業・大企業それぞれに合うツール比較
中小企業には簡易なUIと低コストが特徴のツール、大企業には高度なセキュリティや大規模運用に対応できるツールが適しています。企業規模に応じた選定が必要です。
ローコード開発の選び方のポイント8つ
導入に失敗しないためには、自社のニーズや課題に合ったツールを見極めることが大切です。
ここからは、ローコード開発の選び方について、8つの視点で検討しましょう。
1.自社の開発リテラシーに合ったツールを選ぶ
開発者の技術レベルや社内リソースに応じて、直感的な操作が可能なツールや、自由度の高い開発ができるツールを選ぶと導入後の混乱を避けられます。
2.業務システム or 顧客向けアプリか
社内業務に使うのか、顧客サービスに使うのかで求められる機能が異なります。セキュリティ要件やUI設計のしやすさにも影響します。
3.データ連携やAPI対応は必須か?
既存の基幹システムや外部サービスと連携する必要がある場合は、API対応や連携テンプレートが豊富なツールを選ぶのが賢明です。
4.将来的なスケーラビリティや拡張性
将来の業務拡張を見据えた際、プラグイン追加や機能拡張が可能なプラットフォームであるかどうかも重要なポイントになります。
5.サポート体制の有無
技術的な疑問点にすぐ回答が得られるか、障害発生時の対応スピードなどもツールの使いやすさに影響します。とくに非エンジニアが多い組織では重要です。
6.実績や導入事例の豊富さ
導入実績が多く、業種や規模の近い企業の事例があるツールは、安心感があります。成功事例が多いほど、社内提案もしやすくなるでしょう。
7.操作性(UI/UX)をチェック
ツールの操作感やインターフェースの分かりやすさは、日々の運用効率に直結します。無料トライアルなどで実際に使って確認することが大切です。
8.他システムとの相性とインテグレーション性
他のクラウドサービスや業務システムとスムーズに連携できるかどうかは、長期的な運用効率に大きな影響を与えます。
アプリ開発の見積もりの取り方についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【完全ガイド】アプリ開発の見積もりの取り方|費用の算出方法とポイントを徹底解説
ローコードツールの市場シェアと導入トレンド
ローコード、ノーコード開発ツールは、DX推進や業務効率化の手段として注目されており、国内外で導入が進んでいます。以下では、国内企業の導入率や市場の動向、今後のトレンドについて詳しく解説します。
国内企業の導入率
国内のローコード、ノーコード開発ツール市場は、年々増加しています。とくに、中堅・中小企業においては、迅速な業務改善やコスト削減を目的に導入が進んでいるからです。
今後も、非エンジニアでも扱いやすいツールの普及により、導入率のさらなる向上が期待されます。
注目される背景
ローコード、ノーコード開発ツールが注目される背景には、IT人材の不足やDXの加速があります。、専門的なプログラミングスキルがなくてもアプリケーション開発が可能なツールであるため、業務部門主導での開発が実現できるのが特徴です。
また、開発期間の短縮やコスト削減といったメリットも、導入を後押しする要因となっています。
海外と日本の導入状況の違い
海外では、ローコード、ノーコード開発ツールの導入が進んでおり、とくに北米や欧州での普及率が高い傾向にあります。
一方、日本では、セキュリティや既存システムとの連携といった課題から、導入が遅れている企業も存在します。しかし、最近ではクラウドサービスの普及やベンダーのサポート体制の強化により、日本国内でも導入が加速しています。
業種別の活用事例
製造業では、在庫管理や生産スケジュールの最適化にローコードツールが活用されています。金融業界では、顧客情報の管理やリスク分析の自動化に利用されており、業務の効率化と精度向上に寄与しています。
さらに、医療業界では、患者情報の管理や予約システムの構築など、さまざまな業務に対応するツールとして導入が進んでいるのが現状です。
今後伸びると予測されるツールの傾向
今後は、生成AIとの連携が可能なローコード、ノーコード開発ツールの需要が高まると予測されています。そのため、自然言語でのアプリケーション開発や、より高度な自動化が実現可能となるでしょう。
また、モバイル対応やクラウドベースのツールも、柔軟な開発環境を提供する点で注目されています。
「マルチエクスペリエンス対応」とは
「マルチエクスペリエンス対応」とは、ユーザーがさまざまなデバイスやチャネルを通じて、一貫した体験を得られるようにすることです。ローコード、ノーコード開発ツールでは、スマートフォン、タブレット、PCなど、複数のプラットフォームに対応したアプリケーションの開発が可能です。
マルチエクスペリエンス対応なら、ユーザーエクスペリエンスの向上と、業務の効率化が期待できます。
ノーコードでのアプリ開発なら「ノーコード総合研究所」
株式会社ノーコード総合研究所は圧倒的なスピードでWebアプリや業務システムを開発する、ノーコード開発に特化した国内最大規模の受託開発会社です。ノーコードを用いることで約1/3の期間・費用感での開発を実現します。
AI開発やアプリ開発、Webサイト開発、システム開発までご提供可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
ローコード開発ツールは、IT人材が不足する中でもスピーディかつ柔軟に業務改善を進められる有効な手段です。ツールによって価格や機能が大きく異なるため、自社の予算や開発体制、業務内容に合わせた選定が重要です。
無料プランやトライアルを活用して比較検討することで、導入リスクを抑えながら最適な選択ができるでしょう。

