【徹底解説】ソフトウェア開発におけるNDA(秘密保持契約)とは?メリット・注意点・締結手順を網羅的に紹介!
ソフトウェア開発プロジェクトでは、新しいアイデアや独自技術、企業の内部情報など、多くの機密情報を扱うケースが頻繁にあります。そのような情報が外部に漏れてしまうと、ビジネス上の損害や信用問題に発展するリスクも高まります。そこで重要となるのが「NDA(秘密保持契約)」です。本記事では、NDAの基本的な定義からソフトウェア開発での具体的な活用法、締結の流れや注意点までをわかりやすく解説します。プロジェクトのリスク管理に関心がある方や、初めてNDAを結ぶ開発担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
1 NDA の基礎知識
1-1 NDA の定義と法的根拠
NDA(Non-Disclosure Agreement)とは、取引当事者が共有する機密情報を第三者へ漏えいしないと約束する契約です。日本法では NDA を直接規定する法律は存在しませんが、民法 415 条(債務不履行) や 不正競争防止法 2 条 1 項 7 号 が法的根拠となります。契約条項で秘密情報の範囲・目的外使用の禁止・損害賠償責任を定めることで、流出時に法的な請求根拠が明確になります。
1-2 ソフトウェア開発で NDA が必須となるシーン
ソフトウェア開発では、設計書、アルゴリズム、テストデータ、顧客の個人情報など多岐にわたる秘密情報が扱われます。特に
- 受託開発でソースコードを開示する場合
- PoC(概念実証)段階で技術資料を共有する場合
- OSS に関与するスタッフが並行してクローズド案件に参加する場合
は、競合流出リスクが高まるため NDA が必須となります。
1-3 片務型と双務型 NDA の違い
片務型は「開示側のみ保護し、受領側だけが守秘義務を負う」形態で、アイデア持ち込みフェーズや選考コンペで利用されます。一方、共同開発では双方が情報を出し合うため双務型**が一般的です。双務型では「どちらが提供した情報か判別困難な場合」にも備え、「共同で生じた成果物は共同所有」といった条項を設け、帰属を明確化しておくことが肝要です。

2 NDA を締結するメリット
2-1 アイデア漏えいによる時間的損失の防止
アイデア段階の情報は特許出願前であることが多く、漏えいすれば「先取特許」を抑えられるリスクがあります。NDA を結ぶことで相手方がアイデアを利用しても訴求できる状態を確保でき、新規事業のタイムラインが保護されます。
2-2 関係者の心理的安全性を担保し情報共有を加速
NDA があることで開示側は安心して高粒度の情報を出せるため、不要なマスキングや資料調整が減り、要件定義や技術選定のスピードが向上します。開発スケジュールが短い SaaS 企業ほど、NDA がプロジェクト加速の「潤滑油」として機能します。
2-3 後日の訴訟・損害賠償請求をスムーズに行える
契約書に損害賠償額の予定や差止請求権を明記しておけば、万が一の流出時にも訴訟コストを抑えつつ迅速な救済が可能です。特にクラウドソースコード管理を用いる現場では、ログ解析と合わせて証拠をそろえやすくなり、訴訟リスクを事前にコントロールできます。
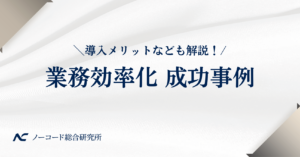
3 NDA を締結する際の主要条項
3-1 秘密情報の定義と除外事由
あいまいな定義では「想定外のデータ」が保護対象外となる恐れがあります。「書面・口頭・電子データを問わず、開示時に機密である旨を示したもの」 と明記しつつ、「公知情報」「独自に創出した情報」は除外するバランスが重要です。
3-2 目的外使用と複製の禁止
ソフトウェア開発では開示資料が GitHub や Notion に複製されるケースが多発します。契約書に「成果物保管場所を限定」「許可なく複写・複製・クラウド共有を禁止」といった条項を入れ、違反時のペナルティを明確化しておきましょう。
3-3 存続期間と返還・廃棄義務
NDA の有効期間は 開示日から 3〜5 年 が一般的ですが、ソースコードのライフサイクルは長いため「契約終了後も○年間は守秘義務が継続」と別条項で定めることが推奨されます。契約終了時には**「全複製物の返還・完全削除を証明する書面」**を要求すると監査対応が容易です。
4 締結までのフローと実務ポイント
4-1 草案作成とレビュー体制の構築
社内リーガル・開発部門・営業部門の 3 者でテンプレート草案を用意し、プロジェクトの機微情報を網羅します。リーガルレビューでは条項の過不足を確認し、開発部門は実装手順や Git の運用ルールと整合するかをチェックすることで、実務とかい離しない契約が作れます。
4-2 電子契約サービスで締結スピードを向上
リモート開発が主流となった現在、DocuSign・GMO サイン・クラウドサイン など電子契約を活用すると平均 1.5 日で締結が完了します。トレーサビリティも確保でき、印紙税も不要になるためコスト削減にも直結します。
4-3 契約管理と監査ログの保管
締結後は契約書 PDF・相手先担当者の連絡先・返還期限を Notion/Confluence に記録し、**「誰が見ても有効期限を把握できる」**状態を保ちましょう。監査対応では「保管ルール」「アクセス権」「削除証跡」が三位一体で求められるため、クラウドストレージの権限を定期的に棚卸しする運用が不可欠です。
5 トラブル事例と対応策
5-1 ソースコード流用発覚事例
自社受託エンジニアが別案件で同じコードを再利用し、機密保持違反となったケースがあります。この場合、NDA に「派生開発禁止」「成果物二次利用禁止」が含まれていなかったため、損害賠償請求が困難でした。解決策として「派生成果物も秘密情報に含む」と追記し、再発防止を図ります。
5-2 オフショア委託先からの無断クラウド共有
海外拠点では Google Drive や Dropbox 共有が慣習化しており、アクセス権のないメンバーに広がった例もあります。対策としては「許可されたストレージ以外へのアップロード禁止」「違反時の即時契約解除条項」を設け、定期的にアクセスログを提出させる監査プロセスを入れることが有効です。
5-3 NDA 締結前の口頭開示トラブル
営業段階で口頭説明したアイデアを先方が製品化してしまったケースでは、証拠不足で訴訟が難航しました。「打ち合わせ前に NDA を締結」「口頭開示は議事録を共有して書面化」 が鉄則です。
6 海外取引での NDA 留意点
6-1 準拠法・裁判管轄の設定
海外ベンダーと契約する場合、日本法準拠・日本の裁判所管轄を希望すると相手が応じないケースが多いです。仲裁機関(JCAA・SIAC など)を利用した国際仲裁条項を盛り込み、中立性を担保しつつ紛争解決を迅速化します。
6-2 輸出規制とデータ越境移転の確認
米国 IT 企業との取引では EAR(輸出管理規則)、EU 企業では GDPR が問題となります。機密情報がソースコードや個人データを含む場合は、輸出許可や SCC(標準契約条項)の締結を要求されることがあるため、社内で法務・情報セキュリティ部門と連携し早期確認が必須です。
6-3 多言語条項の優先順位
英語と日本語の 2 言語で NDA を作成する場合、優先言語条項を明記しないと条文解釈で対立するリスクがあります。「英語版を正文とし、日本語訳は参考」とするケースが一般的ですが、取引額が大きい場合は双方でネイティブレビューを実施し、表現のズレを洗い出しておくと安全です。
まとめ
ソフトウェア開発における NDA は、単なる形式的書類ではなく 「機密情報のライフサイクルを管理するプロジェクトマネジメントツール」 です。
- メリット:アイデアの先取り防止、情報共有スピード向上、訴訟リスク低減
- 締結のカギ:秘密情報の範囲/目的外使用の禁止/存続期間/損害賠償条項
- 運用のコツ:電子契約で迅速締結、契約管理台帳の整備、定期監査ログ確認
- 海外取引:準拠法・輸出規制・優先言語を事前に要チェック
まずは自社テンプレートを整備し、案件ごとに条項をカスタマイズできる体制を作りましょう。万全の NDA 運用が、ソフトウェア開発における競争優位と信頼構築の基盤となります。


