BubbleとDifyの評判を徹底比較|ノーコード×生成AIの評価・事例・課題まとめ【2025年最新版】
1. BubbleとDifyとは?2025年最新版の概要
1-1 Bubbleの特徴と機能範囲
Bubbleは、Webアプリケーションをプログラミングなしで構築できる本格的なノーコードプラットフォームです。フロントエンドからバックエンド、データベース、API連携まで一括で実装可能で、スタートアップから大企業まで世界300万ユーザーが利用しています。ドラッグ&ドロップ式のUI構築や柔軟なワークフロー設計が特徴で、複雑なビジネスロジックや多階層のデータベース構造にも対応できます。近年は日本語教材やスクールも増え、国内での普及が加速しています。
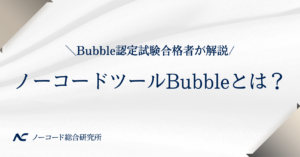
1-2 Difyの特徴と機能範囲
Difyは、ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)をGUIで活用できるオープンソースの生成AIアプリ構築ツールです。ノーコードでチャットボット、RAG(検索拡張生成)、ドキュメントQAなどを実装可能で、企業独自データを安全に扱えるのが強みです。BubbleやAPIとの統合も容易で、業務システムへのAI組み込みが短期間で実現できます。近年はクラウド版(SaaS)も安定し、日本国内の企業導入が急増しています。

1-3 ノーコード×生成AI市場の背景
2024年以降、生成AIの進化とノーコード開発の普及が重なり、非エンジニアでも高度なAIアプリを短期間で構築できる環境が整いました。特に中小企業やスタートアップは、開発コスト削減と市場投入スピード向上のためにノーコード×生成AIの導入を加速。BubbleとDifyは、それぞれ「業務アプリ構築」と「AI機能埋め込み」の領域で高い評価を得ており、両者の組み合わせは業務効率化や新規サービス立ち上げにおける有力な選択肢となっています。
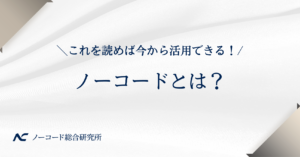
2. Bubbleの評判と利用シーン
2-1 ポジティブ評価とその理由
Bubbleは「ノーコードながら複雑なアプリ構築が可能」という点で高評価を得ています。API連携や外部サービスとの統合が柔軟で、データベース設計も直感的。UIは完全GUIで構築でき、マルチページやユーザー管理などWebサービスに必要な要素を標準搭載しています。海外では「ノーコードの中で最も自由度が高い」と評され、プロトタイプから本番運用まで一気通貫で開発できる点が支持されています。SaaS開発や業務システム構築に適したツールとして広く認知されています。
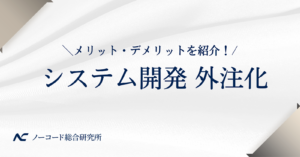
2-2 ネガティブ評価と改善傾向
一方で「学習コストが高い」という声もあります。特にワークフローや状態管理の概念を理解するまで時間がかかるケースが多いです。また、過去には日本語情報が乏しくUIカスタマイズの自由度にクセがあると指摘されました。しかし2024年以降は、日本語解説やテンプレート、オンライン講座の充実により国内ユーザーの参入障壁が低下。さらにプラグインマーケットプレイスも拡大し、機能拡張のしやすさも向上しています。
2-3 代表的な国内外の活用例
海外では不動産予約システムやフィンテックアプリ、教育プラットフォームなど多様な分野で活用されています。国内でもスタートアップがSaaS型サービスを短期間でローンチする事例や、中小企業が顧客管理システム(CRM)を独自開発する事例が増加。特に「既存業務のシステム化を外注せず自社で内製化したい」というニーズにマッチし、ノーコードでのMVP開発から本格運用まで活用されるケースが目立っています。

3. Difyの評判と利用シーン
3-1 高評価ポイントと利用メリット
Difyは「生成AIを業務アプリに組み込みやすい」という点で高く評価されています。特にRAG機能により、自社データベースやドキュメントを元にした自然言語応答を実現でき、情報漏洩リスクを低減できます。Bubbleとの相性も良く、ノーコードで作成したUIにDifyのAI機能を組み込むことで、社内外の問い合わせ対応や営業支援を自動化可能。OSSであるためカスタマイズの自由度も高く、企業の要件に合わせた最適化がしやすいです。
3-2 改善が必要な点と現状
導入初期はドキュメントが中国語や英語中心で、日本語ユーザーには敷居が高いという課題がありました。また、クラウド版が安定するまでは自己ホスティングが必須で、サーバー運用リソースが必要でした。しかし2025年現在、公式SaaS版が安定稼働しており、UIの多言語化や設定ガイドの充実が進んでいます。GitHubコミュニティやDiscordでの情報共有も活発化し、日本語の技術記事や導入事例も増加中です。
3-3 導入事例から見る有効性
国内では、カスタマーサポート企業がDifyを使ってFAQ対応チャットボットを構築し、オペレーターの対応工数を50%以上削減した事例があります。また教育業界では、教材PDFを取り込んで質問応答できる学習支援AIを短期間で開発。海外では医療、法律、金融分野でもナレッジ検索や文書解析に利用され、業務効率化だけでなく顧客満足度向上にも寄与しています。

4. BubbleとDifyの連携メリット
4-1 フロントエンド×AI連携の強み
Bubbleはユーザーインターフェース(UI)と業務ロジックの構築に強く、Difyは自然言語処理や情報検索に特化しています。この2つを連携させることで、例えば顧客マイページ内でAIチャットを提供するなど、UIとAIがシームレスに統合された体験を実現できます。ユーザーはアプリの画面遷移なしに、入力フォームやチャットを通じて高度なAI機能を利用でき、顧客満足度や業務効率を同時に向上させられます。

4-2 データベース連動による効率化
Bubbleは関係型データベースをGUIで設計でき、Difyにそのデータを連携させることで、動的なAI応答が可能になります。例えば、不動産物件情報や顧客購入履歴をBubbleで管理し、Dify経由で自然言語検索やおすすめ提案を返すことができます。この仕組みにより、複雑なクエリや外部検索エンジンを使わずに、高度なパーソナライズ対応を短期間で実装できます。
4-3 外部サービス連携の幅広さ
BubbleはWebhookやAPIで外部システムと双方向連携でき、Difyも外部データソースやクラウドストレージに対応しています。これにより、CRM、ERP、在庫管理システム、決済サービスなどの既存業務インフラとAI機能を一元的に統合可能です。結果として、複数ツール間でのデータの重複管理や手動更新が不要になり、業務フロー全体を自動化することができます。

5. 実際の導入事例(国内外)
5-1 営業支援チャットボット
あるITベンチャーでは、Bubbleで営業チーム専用のダッシュボードを作成し、Difyで製品カタログPDFや提案資料を取り込んだQA機能を搭載。顧客からの質問にAIが即時回答し、営業担当者は必要な場合のみ対応する形に変更しました。その結果、問い合わせ対応時間は従来比で約90%削減され、商談準備にかける時間を新規開拓や戦略立案に振り向けられるようになりました。

5-2 不動産内見サポートAI
不動産会社では、Bubbleで物件検索や予約フォームを構築し、Difyを使って物件データベースを自然文で検索できるようにしました。顧客は「駅から徒歩5分以内、築10年以内の3LDK」などと入力するだけで候補が一覧表示されます。結果として、営業担当の内見同伴回数が減少し、効率的な案内が可能になり、契約率も向上しました。
5-3 社内ナレッジ検索エンジン
教育サービス企業では、Difyに社内マニュアルや研修資料をアップロードし、Bubbleで検索UIを構築。新人研修中の質問にAIが即答する環境を整え、トレーナーへの質問件数を大幅に削減しました。結果、研修期間が短縮され、早期戦力化が実現。属人化していたノウハウの共有も効率的に行えるようになりました。
6. ユーザー評価まとめ
6-1 海外ユーザーの声
RedditやProduct Huntでは、「BubbleとDifyの連携はノーコードAIアプリ開発の最適解」という意見が多数。特に短期間でのプロトタイプ作成やUIの自由度、AI機能の強化が評価されています。「数日でデモ版を完成させ、投資家に提示できた」というスタートアップの声もあり、迅速な市場投入の手段として活用されています。
6-2 国内ユーザーの声
国内ではX(旧Twitter)やQiitaにて「ノーコードでRAG実装できるのは画期的」といった意見が多く見られます。Bubbleの自由度とDifyのAI機能がうまく噛み合い、非エンジニアでも高度なアプリ開発が可能になったという評価が目立ちます。一方で「日本語ドキュメントがまだ足りない」という声もあり、学習コンテンツの充実が今後の課題とされています。
6-3 評価から見える傾向
総合的に見ると、Bubble×Difyの評価は非常に高く、特に中小企業や新規事業チームからの支持が厚いです。理由は、低コストで短期間にAI搭載型アプリを構築できる点と、運用中の仕様変更にも柔軟に対応できる点です。唯一の課題は学習コストですが、テンプレートや事例が増えることで解消に向かっています。
7. 導入時の注意点と課題
7-1 学習コストとサポート活用
Bubbleは自由度が高い反面、データベース設計やワークフロー管理の理解に時間がかかります。DifyもAI構築に必要な概念(プロンプト設計やRAG構造)を理解する必要があります。初期導入時は公式チュートリアル、オンラインスクール、代理店サポートを併用することで学習時間を短縮できます。
7-2 バージョンアップ対応
DifyはOSSで開発が進んでいるため、機能追加やUI変更が頻繁に発生します。導入企業はGitHubや公式Discordで最新情報を常にチェックし、開発環境と本番環境を分けてアップデート検証を行うことが推奨されます。Bubbleも機能追加が行われるため、更新時の互換性確認が必要です。
7-3 セキュリティ設計の重要性
特に個人情報や機密情報を扱う場合、APIキー管理や通信暗号化、アクセス制御を適切に設計する必要があります。BubbleとDify間の通信はHTTPSで暗号化されますが、サーバー側でのデータ保持ポリシーやログ管理も含めた全体設計を行うことが重要です。
8. 他ノーコード×生成AIツールとの比較
8-1 Glide × ChatGPT API
GlideはGoogleスプレッドシートやExcelをデータベースとして利用できるノーコードツールで、表計算型UIが得意です。ChatGPT APIと連携すれば、簡単なAIチャットや文章生成が可能ですが、複雑な業務ロジックやデータベース間の関係性管理には制限があります。社内ツールや簡易アプリには適していますが、外部顧客向けの高度なWebサービスには機能不足になる場合があります。

8-2 Softr × Dify
SoftrはAirtableやGoogle SheetsをベースにWebアプリを構築でき、シンプルなUIデザインと早期立ち上げに強みがあります。Difyと連携すれば、社内ポータルやFAQ検索AIを短期間で作成可能です。ただしUIカスタマイズの自由度や大規模データ処理能力ではBubbleに劣ります。テンプレートを活用し、社内利用や限定公開型のAIツールを作る場合に向いています。
8-3 Retool × OpenAI
Retoolはエンジニア向けのローコードツールで、SQLやJavaScriptを直接記述して柔軟な業務アプリを構築できます。OpenAIとの連携で高度なAI処理を実装可能ですが、プログラミング知識が必要なためノーコード初心者には敷居が高めです。既存システムやAPIを駆使した業務改善を迅速に行いたいエンジニアチームに適しています。
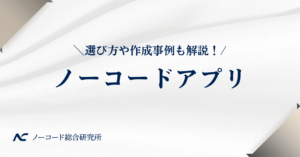
9. 導入手順とおすすめ活用法
9-1 無料版での検証方法
BubbleとDifyはどちらも無料プランを提供しており、初期投資ゼロで検証可能です。まずは小規模なプロトタイプを作り、UIの操作感やAI応答の精度を確認します。この段階で、データベース設計やAPI連携の基本を習得し、チーム内で操作を共有しておくと、本格導入時のトラブルを防げます。
9-2 小規模プロジェクトでの活用
初期導入では、既存業務の一部を置き換える形から始めるのがおすすめです。例えば、営業部門のFAQ対応や社内資料検索など、効果が可視化しやすい領域から着手します。短期間で成果を出せれば、社内の理解と導入推進力が高まり、他部署への展開もスムーズに進みます。
9-3 本格運用に向けた準備
本格運用を始める前に、セキュリティポリシー策定、運用ルールの明文化、バージョン管理体制の確立を行います。また、AI応答の品質を維持するため、定期的なプロンプト改善やデータ更新を実施します。必要に応じて外部パートナーと連携し、開発・運用体制を強化することが重要です。
10. まとめ|Bubble×Difyの今後の展望
10-1 2025年以降の市場予測
ノーコードと生成AIの組み合わせは、非エンジニアが自社専用のAI搭載アプリを開発できる時代を加速させます。特にBubbleとDifyは、UI構築とAI統合の両輪として強い存在感を持ち、SaaSや業務アプリ市場でのシェア拡大が見込まれます。
10-2 自社導入時の判断ポイント
導入の判断基準は「短期間で価値を生み出せるか」「運用コストを抑えられるか」「既存業務と親和性が高いか」の3つです。Bubble×Difyはこの条件を満たしやすく、特に中小企業や新規事業部門でのROI(投資対効果)が高い傾向があります。
10-3 試してみるべき理由
無料で始められ、少人数でも本格的なAI搭載アプリを構築可能な点は大きな魅力です。試作段階で得られるフィードバックは、フルスクラッチ開発に比べ大幅に早く、開発リスクを低減します。まずは小さな案件から試し、自社に最適な活用方法を見つけることをおすすめします。
