Difyの最新機能まとめ|2025年注目アップデートと活用術
ノーコードでAIアプリを構築できるツール「Dify」は、近年急速に注目を集めています。特に2025年に入ってからは、より実務に役立つ多機能化が進み、エンジニアではないビジネスマンにとっても使いやすいツールへと進化しています。
この記事では、Difyの最新機能を網羅的に解説しつつ、どのように日々の業務に取り入れられるのかをわかりやすく紹介します。「業務を自動化したい」「社内に生成AIを導入したい」「AIアプリを簡単に作りたい」と考えている中間管理職の方は、ぜひ最後までご覧ください。
最新アップデート概要(2025 年版)
Workflow 正式実装で「対話を超える」自動化プラットフォームへ
2024 年後半からベータ提供されていた Workflow 機能が、2025 年春に正式版としてリリースされた。GUI 上で Trigger → Condition → Action を直感的に並べるだけで、メール受信・フォーム送信・時間指定などを起点に AI 呼び出しや外部 API 連携をチェーン化できる。Zapier や IFTTT の概念を踏襲しつつ、各ステップに LLM の推論を挟める点がユニークで、「入力内容を要約して判定」「感情分析して分岐」「HTML 生成して送信」といった“AI 付き自動化”がノーコードで構築可能になった。
RAG 高度化で社内ナレッジ活用をさらに加速
ファイルアップロード→即検索という従来の簡易 RAG に加え、2025 年バージョンでは 階層メタデータ と 意味クラスタリング が実装された。章タイトル・作成者・機密区分など複数ラベルを付与でき、検索時に「営業向け資料だけ」「最新版のみ」といったフィルタリングが可能になったほか、意味ベクトル空間で内容が近い文書を自動クラスタリングするダッシュボードも追加。新人が「顧客提案の成功事例」と入力すれば、関連スライド・議事録・Slack 会話まで横断的に提示され、社内知識探索が飛躍的に効率化する。
Plugin SDK が拓く “社内情報ハブ” 構想
Plugin SDK は OpenAPI スキーマをアップロードするだけで外部サービスを Dify 内に統合できる機能だが、2025 年版では 双方向 Webhook と 権限委譲トークン に対応した。これにより、Slack→Dify→Jira→Slack という循環フローをワンクリックでデプロイできるほか、プラグインごとにアクセスキーを分離し最小権限原則を徹底できる。社内では「メッセージング+生成 AI+業務 SaaS」を束ねる 中央制御室 として Dify を位置付ける動きが加速している。
AI Agent 2.0:タスク分解とマルチステップ実行が完全自律化
新バージョンのエージェントは メモリストア と プランナー を搭載し、目標達成のために自ら情報検索→計画立案→実行→検証をループする。本来人間が行っていた「結果が微妙だから手直しして再実行」を AI が自律で繰り返すため、マーケ提案書作成のように試行錯誤が多いタスクで威力を発揮。βテスト企業では、競合分析レポート作成時間が 6 時間から 25 分に短縮された実績が報告されている。

Workflow 機能で業務を自動化
トリガー設計:人・時間・データの 3 方向で起動
Workflow は Human trigger(チャット入力やボタン押下)、Schedule trigger(毎時/毎日/Cron)、Event trigger(外部 Webhook 受信) の 3 系統を組み合わせて起動条件を定義できるため、たとえば“月初に全営業の活動記録を要約→Slack 通知→CSV 生成→Google Drive に保存”というマルチステップ処理を完全無人化できる。
条件分岐とデータ変換で複雑ロジックをノーコード実装
条件ステップでは「含む/一致/正規表現」といったテキスト判定や数値比較が用意され、SQL を書かずとも入力値に応じてフローを分岐できる。Map/Reduce ノードでは JSON キー名の置換や配列のフィルタがドラッグ操作で構築でき、外部 API のレスポンス整形もプログラムレスで完結。
監視・アラートで運用負荷を最小化
Workflow 実行履歴はタイムライン形式で確認でき、失敗時にはメール・Slack・PagerDuty へ自動通知。再実行ボタンでリトライも可能だ。運用担当者はエラー発生時のログをクリックすると AI が原因分析と改善提案を提示するため、非エンジニアでも安定稼働を維持できる。

RAG(外部データ連携)の進化
マルチソース・マルチフォーマット取り込みの高速パイプライン
アップロード画面が刷新され、ドラッグ&ドロップで PDF・PPTX・Excel・CSV・HTML をまとめて投入すると、バックエンドがファイル種別ごとに最適なパーサーを自動選択し、最短数秒でベクトルインデックス化。Google Drive/Notion/Box といったクラウドソースも OAuth で接続するだけで、指定フォルダを定期クロールし差分同期する。
意味検索とメタデータフィルタで“探す”から“辿り着く”へ
高精度埋め込みモデル(text‑embedding‑3)が標準採用され、キーワードが一致しなくても意味的に近い文書が上位表示される。さらに「author:山田」「tag:国際展開」のようにメタ情報で絞り込み、回答出力時には引用文のページ番号とハイライト付き PDF へのディープリンクが自動生成されるため、裏付け確認が一瞬で完了する。
データガバナンス:アクセス制御とバージョン管理
ナレッジごとに公開範囲を Only me/Team/Custom で設定でき、閲覧権限を持たないユーザーには検索結果自体が表示されない。ファイル差し替え時は旧バージョンが自動バックアップされ、誤削除も即復旧可能。データ生命周期を可視化することで、機密情報取り扱いに厳しい業界でも導入しやすい。
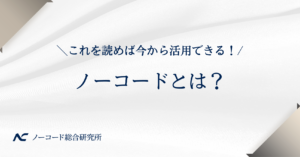
AI Agent の高度化と自律性の強化
メモリストアによる長期タスクのコンテキスト保持
エージェントは実行途中で得た情報をベクトル DB に逐次書き込み、タスク継続中に再利用する。これにより「競合 A の資金調達情報を把握→次に B 社を調査→最後に比較表を作成」という長期ワークフローでも、一貫した観点でアウトプットを生成できる。
プランナー×ツールチェーンで多段処理を自動化
ユーザーが“市場参入戦略を作って”と依頼すると、エージェントは①ターゲット市場特定→②SWOT 分析→③競合比較→④戦略立案→⑤ KPI 設定というサブタスクへ自動分解。各ステップで RAG や外部 API を呼び、完了を確認して次工程へ進むため、最終成果物は PPTX+ Excel の形で一括納品される。
モニタリング UI とヒューマンインザループ
エージェントの行動はリアルタイムでダッシュボード表示され、中断・手動介入も可。誤った方向へ進みそうなときに「STOP」ボタンでハルシネーション拡散を防ぎ、マネージャーが指示を与えて再開するハイブリッド運用が実現する。
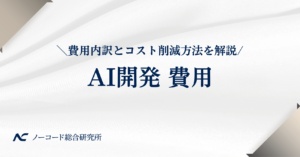
Plugin SDK で API 接続が自由自在
OpenAPI を読み込むだけのワンステップ登録
Swagger/Postman ファイルをアップロードすると、エンドポイントと引数が自動マッピングされ、AI から関数呼び出し可能になる。API キーは暗号化ストアへ保存され、ローテーションにも対応。
双方向 Webhook とイベントドリブン連携
プラグインは HTTP リクエストを送るだけでなく、外部サービスからの Webhook を受信し Workflow を起動できる。たとえば「Slack で 👍 リアクションが付いたらタスクを Done に更新」「Stripe の支払い成功でサンクスメールを AI が生成→送信」など、イベントドリブン自動化をシームレスに実装できる。
パーミッション分離と監査証跡
プラグインごとにアクセストークン scope を限定し、必要最小限の権限だけを付与。呼び出しログはプラグイン単位でフィルタリングでき、問題発生時の責任切り分けが容易だ。
Google Sheets との統合機能
インプット&アウトプットの両方向シンク
AI が生成した表データを指定シートに即書き込み、逆にシート側でセル更新が発生すると Workflow トリガーで AI が再計算・要約するフィードバックループを構築。個別の GAS(Apps Script)をメンテナンスする必要がなくなる。
リアルタイム集計と可視化
毎晩定刻で売上データを取り込み、AI が要約ポイントと異常値を挙げた上でグラフ付きダッシュボードシートを生成。経営会議用レポート作成時間をゼロにし、担当者は分析コメントのブラッシュアップに集中できる。
テンプレート化で多部署展開
「案件管理」「仕入集計」「顧客属性分析」などユースケース別テンプレートを配布すると、非エンジニアの現場担当でもコピペだけで導入可能。社内展開速度が加速し、情報基盤の標準化が進む。
チーム機能の強化で社内導入が進めやすい
役職別ロールによる最小権限運用
Owner は課金設定とプラグイン管理、Editor はプロンプト編集、Viewer は実行権のみといった階層分離が UI 上でワンクリック。退職者や外部委託先のアカウントを即無効化でき、ガバナンスを担保。
プロジェクトとナレッジの分離管理
営業用ボットと開発用 RAG を同一ワークスペースで運用しつつ、閲覧範囲をプロジェクト単位で制限。社外秘情報へのアクセスを部署横断でコントロールできるため、大規模組織でも導入ハードルが低い。
操作ログと監査レポート
全ユーザーのプロンプト変更・ファイルアップロード・API 呼び出しが監査ログに記録され、期間指定で CSV エクスポート可能。内部統制や ISMS 監査での提出資料作成が数クリックで完了する。
UI 改善と日本語対応の向上
テンプレートウィザードで 10 分デプロイ
チャットボット/要約ツール/ドキュメント検索の 3 大テンプレを選ぶと、画面がステップ形式で必要項目(モデル・データソース・回答形式)を案内。フォーム記入後に「Deploy」を押せば即動作確認でき、初心者でも迷わない。
ドラッグ&ドロップによるワークフロー編集
Workflow 画面はノードをキャンバスにドラッグし、線をつなぐだけで処理順序を定義可能。ノード説明も日本語化され、「条件分岐」「LLM 呼び出し」「メール送信」といった名前で直感的に理解できる。
インラインガイドとツールチップ
各設定項目の右端に「?」アイコンが付き、日本語の詳細解説がポップアップ。ドキュメントを逐一検索せずに設定の意味を理解できるため、学習コストが大幅削減された。

セキュリティ・データ管理面の強化
マルチテナント設計でデータ完全分離
同一 SaaS インスタンスでもワークスペース間で DB テーブルとストレージバケットを完全分割。ユーザー誤設定やシステムバグで他テナントへデータが漏れるリスクを根本排除。
シークレットストアとキー管理
API キーや DB パスワードは KMS と連携した安全領域へ暗号化保存し、UI 上では復号表示不可。サービスアカウント発行・失効をロールベースで制御し、キー漏洩リスクを極小化。
監査ログと Export 機能
全リクエスト・レスポンスを JSON ログとして最長 1 年保管。GUI から期間・ユーザー・アプリ単位でフィルタし、Click‑Once でダウンロードできるため、外部監査での提出コストが激減する。
Open Source 版と SaaS 版の違い
OSS 版:自由度とカスタマイズ性を最大化
Docker Compose で即構築でき、フロント UI やバックエンドを自由に改変可能。社内 GPU を使ったオンプレ推論や SSO 連携など独自要件を満たしやすいが、アップデート適用と障害対応は自主管理となる。
SaaS 版:運用レスで最新機能を即享受
月額課金でアカウント即発行、サーバメンテやセキュリティパッチは運営側が担うため IT 部門の負荷がゼロ。プラグインカタログやテンプレートが随時追加されるため、非エンジニア組織でも短期間に全社展開が可能。
ハイブリッド導入も選択肢
PoC は SaaS 版でスピード重視、全社本番は OSS 版を VPC 内で運用という“段階移行モデル”も推奨される。従量 API コストを抑えるため、OSS 版で OSS LLM を動かしつつ、重要タスクのみ SaaS 版の GPT‑4 を呼ぶハイブリッド構成が注目されている。
これからの Dify の展望と活用戦略
全社 DX 基盤としてのポジショニング
社内チャットボットや FAQ を入り口に、RAG・Workflow・Agent を段階的に組み合わせることで、データ検索→情報生成→業務実行を一枚岩で提供する「AI ネイティブ業務基盤」へ進化。IT 部門は Dify を中核に置き、周辺 SaaS とプラグインで疎結合する戦略が主流になる。
スモールスタートから全社展開へのロードマップ
- 部署内課題を 1 か月で PoC → 2) 効果を KPI で可視化し他部署に横展開 → 3) 会社方針としてプラグイン/RAG ガバナンスを整備 → 4) 全社標準ツール化しワークフローを共通テンプレート化、という 4 段ステップが最も失敗が少ない。
生成 AI ガバナンスと TechOps 体制の構築
API コスト・誤回答率・機密情報取り扱いを可視化し、改善責任を担う PromptOps チームを編成。定例レビューでログを分析し、モデル選択・プロンプト最適化・プラグイン管理を継続的に行うことで“野良ボット乱立”を防ぎながら価値を最大化できる。
まとめ
Dify は 「作る」「連携する」「自動化する」 をワンストップで実現する次世代業務プラットフォームへ進化した。
- Prompt‑as‑App によるノーコード開発で PoC を爆速化
- Workflow/Agent/Plugin SDK による自律型業務フローを実現
- RAG 高度化+マルチモデル でナレッジ活用とコスト最適化を両立
- チーム・セキュリティ機能強化 でエンタープライズ導入の壁を突破
中間管理職が抱える「人手不足」と「業務属人化」という永年課題を、低コストかつ短期間で解決できる選択肢が Dify である。まずは小さな業務ボトルネックを Dify に任せ、効果を数字で可視化した上で全社展開へ広げてほしい。AI が単なるチャット相手から 実務を担う戦力 に変わる瞬間を、あなたのチームで体験できるはずだ。
